本文
紫式部文学賞 - 受賞作品

第35回紫式部文学賞
受賞作品:『大使とその妻』
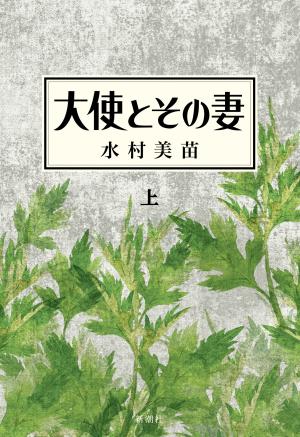
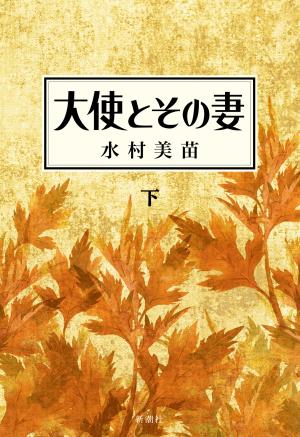
著者: 水村 美苗 (みずむら みなえ) さん
作品紹介と講評(鈴木 貞美 選考委員長)
ゲイのアメリカ人男性・ケヴィンがコロナ禍を避けて、人里離れた追分の山小屋で、はじめて冬を越そうと思い立ち、日本語で手記を綴りはじめる。彼は、将来を嘱望された兄が運転していた車の事故で亡くなり、劣等感に苛まれたまま、父親からは見放され、兄が死んだのはおまえのせいだと責める姉と縁を切り、シカゴを離れて東京で動画サイト「失われた日本を求めて」を立ち上げていた。それは父親歿後、資産を受けついだ日本趣味の外国人ならでは、の企画だった。
その前の年、彼は、京都の宮大工を入れて隣の山荘を改築して越してきた外交官・篠田氏の夫人・貴子が夜の露台で狂気を孕んだ薪能を舞う姿を垣間見て、深く惹かれ、夫妻と親交を重ね、彼女の数奇な生い立ちを知ってゆく。貴子は、第二次世界大戦後、ブラジルで日本の勝ちを信じ、敗戦を認める同胞と死闘を繰り広げた「勝ち組」の男の娘に生まれた。父親はサンパウロの日本人街で書店を営む夫婦に娘を託し「ちゃんとした日本人」に育ててくれと言い残して姿を消した。貴子は、恋愛沙汰を起こして政治家の父親から勘当され、サンパウロにやってきた女性に見込まれ、幼いときから能の舞を仕込まれた。やがて日系ブラジル人のために弁護士になった貴子は篠田大使と結ばれ、「日本の土に還りたい」と願いを抱いて、変貌著しい京都に暮らしはじめると、パニック発作に襲われるようになった。彼女の心の病を癒すため、夫妻は山荘に引きこもり、和風趣味を演じることを自ら「ニッポンごっこ」と呼んでいた。ふと、今日、浮遊する「日本らしさ」の象徴か、などと想いもする。だが、いま、夫妻は再び南米に飛んだのか、隣の山荘に人影はない。
篠田夫妻のほか、ケヴィンの交遊録は際立って個性の強い外国人と、さほどでもない日本人を取り混ぜて織りなす人生模様は興味つきない。それでいてデリカシーに満ちているのは、グローバリゼイションの渚のあたりを漂う人々ゆえか。
ケヴィン自身は、といえば、貴子が何気なく漏らした一言から、姉が心に宿していた罪障感に思い至り、ZOOMで交信を重ねてその仲を修復してゆく。回想を綴るうちには、兄への劣等感から解き放たれていった経緯も蘇る。若き日に失った自分を取り戻した彼のもとに、篠田氏を失い、通信が途絶えたままだった貴子から和風趣味の封筒が届いて、手記は閉じる。
作品紹介と講評(竹田 青嗣 選考委員)
舞台は軽井沢追分。俗世から離れた孤独な翻訳者ケヴィンは、隣家の元外交官篠田夫妻と交流するが、美しい能を舞うその妻貴子のたたずまいに強く引かれ、彼女の数奇な来歴を書きつづろうとする。物語は、ブラジル移民の子として現地で育った貴子が、さまざまな人物と出会いながら不思議な仕方で日本的な文化を身につけてゆく経緯が描かれる。大きな歴史の流れと小さな人間の悲しみや夢のクロニクルといえるような物語が、いくつもの流れをともなって展開する。月から降りてきたこの世ならぬ高貴さをもつ「かぐや姫」的な貴種流離譚とも、時間と記憶が不思議に交錯するプルースト的な物語の日本版とも読める。ストーリーの複数性、多彩なモチーフを自在に繰り広げながら、それらを収斂させてゆく文学的な手腕は読者を堪能させる。最後に、なぜ人は「美しいもの」に引かれるのだろうかという問いが、静かに心に残るような小説だ。
受賞の言葉
このたびは紫式部文学賞を賜り、心より感謝を申し上げます。これ以上大きなお名前はない賞です。日本が世界にもっとも誇れるものを一つだけ挙げよ――そう言われたら、世界の人は、少しでも教養があれば、迷わずに『源氏物語』の名を挙げるでしょう。今から一千年以上も前に私たちの言葉で書かれ、そして読みつがれてきた、かくも奥の深い文学があったという事実。しかもその文学が女の人の手によるものであったという事実。それはこの先何があろうと人類が存在する限り消すことのできない、歴史的、文学的事実です。文学は過去の文学を糧として生まれます。今回この賞を賜り、自分が書くものがそのような文学とつながっているという幸福、いや、女の物書きとしてより深くつながっているという幸福を、高らかに謳い上げたい気持です。もう作家としての年月が限られた身ではありますが、書き続けられるだけ書き続けたく思っております。ありがとうございました。

著者略歴
昭和26年、東京都生まれ。
12歳のときに父の仕事の都合で渡米し、以来米国で教育を受ける。
イェール大学大学院仏文科博士課程修了。
小説家・評論家として幅広く活躍中
これまでの受賞作品
| 開催回 | 受賞作品 | 発行者 | 受賞者 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 『式子内親王伝 -面影びとは法然-』 |
朝日新聞社 | 石丸 晶子 |
| 第2回 | 『きらきらひかる』 | 新潮社 | 江國 香織 |
| 第3回 | 『十六夜橋』 | 径書房 | 石牟礼 道子 |
| 第4回 | 『淀川にちかい町から』 | 講談社 | 岩阪 恵子 |
| 第5回 | 『アムリタ』 | ベネッセコーポレーション | 吉本 ばなな |
| 第6回 | 『夫の始末』 | 講談社 | 田中 澄江 |
| 第7回 | 『蟹女』 | 文藝春秋 | 村田 喜代子 |
| 第8回 | 『齋藤史全歌集』 | 大和書房 | 齋藤 史 |
| 第9回 | 『神様』 | 中央公論新社 | 川上 弘美 |
| 第10回 | 『薬子の京』 | 講談社 | 三枝 和子 |
| 第11回 | 『釋迢空ノート』 | 岩波書店 | 富岡 多惠子 |
| 第12回 | 『歩く』 | 青磁社 | 河野 裕子 |
| 第13回 | 『浦安うた日記』 | 作品社 | 大庭 みな子 |
| 第14回 | 『愛する源氏物語』 | 文藝春秋 | 俵 万智 |
| 第15回 | 『ナラ・レポート』 | 文藝春秋 | 津島 佑子 |
| 第16回 | 『沼地のある森を抜けて』 | 新潮社 | 梨木 香歩 |
| 第17回 | 『歌説話の世界』 | 講談社 | 馬場 あき子 |
| 第18回 | 『とげ抜き 新巣鴨地蔵縁起』 | 講談社 | 伊藤 比呂美 |
| 第19回 | 『女神記』 | 角川書店 | 桐野 夏生 |
| 第20回 | 『ヘヴン』 | 講談社 | 川上 未映子 |
| 第21回 | 『尼僧とキューピッドの弓』 | 講談社 | 多和田 葉子 |
| 第22回 | 『評伝 野上彌生子 -迷路を抜けて森へ』 |
新潮社 | 岩橋 邦枝 |
| 第23回 | 『東京プリズン』 | 河出書房新社 | 赤坂 真理 |
| 第24回 | 『『青鞜』の冒険 女が集まって雑誌をつくるということ』 |
平凡社 | 森まゆみ |
| 第25回 | 『晩鐘』 | 文藝春秋 | 佐藤 愛子 |
| 第26回 | 『戯れ言の自由』 | 思潮社 | 平田 俊子 |
| 第27回 | 『浮遊霊ブラジル』 | 文藝春秋 | 津村 記久子 |
| 第28回 | 『えぴすとれー』 | 本阿弥書店 | 水原 紫苑 |
| 第29回 | 『パンと野いちご 戦火のセルビア、食物の記憶 | 勁草書房 | 山崎 佳代子 |
| 第30回 | 『夢見る帝国図書館』 | 文藝春秋 | 中島 京子 |
| 第31回 | 『組曲 わすれこうじ』 | 新潮社 | 黒田 夏子 |
| 第32回 | 『夕暮れに夜明けの歌を 文学を探しにロシアに行く』 | イースト・プレス | 奈倉 有里 |
| 第33回 | 『イコ トラベリング 1948ー』 | 角川書店 | 角野 栄子 |
| 第34回 | 『風配図 WIND ROSE』 | 河出書房新社 | 皆川 博子 |






