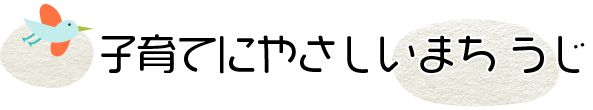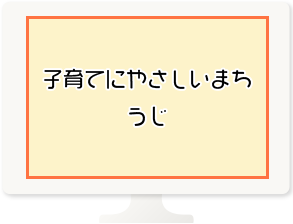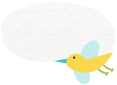本文
ひとり親家庭自立支援事業について
この事業は、ひとり親家庭のお母さん、お父さんが就職に有利な資格や技能を取得することで、より安定した生活を送れるように支援することを目的としています。
自立支援教育訓練給付金事業
就職に必要な資格や技能を身につけるため、指定された教育訓練講座(医療事務、介護職員研修、情報処理など)を受講する場合に費用の一部を支給します。
必ず事前にご相談ください。
対象者
宇治市内在住のひとり親家庭の親(20才未満の子を扶養している方)
支給要件
- 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること
- 講座を受講することが、就職やキャリアアップのために必要であると認められること
- 過去に本事業による教育訓練給付を受けていないこと
※講座受講開始前に講座を指定するためのお手続きが必要です。
対象講座
- 雇用保険法による「一般教育訓練給付金」の指定講座
- 雇用保険法による「特定一般教育訓練給付金」の指定講座
- 雇用保険法による「専門実践教育訓練給付金」の指定講座
※厚生労働省 教育訓練給付制度<外部リンク>
※厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム<外部リンク>
支給額
受講者が支払った教育訓練経費の60%相当額
12,001円以上、上限20万円。専門実践教育訓練の指定講座は、40万円×修業年数(上限160万円)。
雇用保険法に基づく教育訓練給付金を受けることができる方は、その給付金との差額。(下限12,001円)
※経費とは、教育訓練施設に支払った入学料、授業料及び消費税のうち、教育訓練施設の長が証明する経費が対象です。ただし、希望により行われる訓練や提供される教材等に要する費用は除きます。
※厚生労働省 教育訓練給付制度<外部リンク>
申請手続
講座指定の手続きが必要ですので、受講を希望する講座の受講開始日前に講座指定の申請をしてください。
また、講座を修了したときは、受講修了日から1か月以内に支給申請をしてください。
【受講前】
講座指定の申請 →指定決定→ 講座を受講
<必要書類> 公簿等で確認できる場合には省略可
- 申請者及びその児童の戸籍謄本または抄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 母子・父子自立支援プログラムの写し等
- 雇用保険制度の教育訓練給付金支給要件回答書(管轄のハローワークが発行)
- 受講講座のパンフレット(費用、受講期間のわかるもの)
- 申請者のマイナンバーの確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバー記載の住民票の写しのいずれか)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
【受講後】
支給申請(受講修了後1か月以内)→ 支給決定 →支給
※雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を受ける方は、受講修了後ハローワークにもお手続きください。
<必要書類> 公簿等で確認できる場合は省略可
- 申請者及びその児童の戸籍謄本または抄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 母子・父子自立支援プログラムの写し等
- 対象講座指定通知書
- 指定講座の修了証明書
- 教育訓練経費の領収書
- 教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(雇用保険制度の教育訓練給付金の受給資格がある方のみ)
- 申請者のマイナンバーの確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバー記載の住民票の写しのいずれか)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
マイナンバーについて
平成28年1月からマイナンバーの利用開始に伴い、自立支援教育訓練給付金の手続きの際には、マイナンバーの記入が必要です。マイナンバーの確認できる書類と本人確認書類をお持ちのうえ、お手続きください。
詳しくはこども福祉課窓口におけるマイナンバー確認と本人確認について(別ウインドウで開く)。
高等職業訓練促進給付金事業
就職に有利な資格を取得するため、専門学校等の養成機関で修業する場合に、生活の負担の軽減を図り資格の取得を容易にするために給付金を支給します。
必ず事前にご相談ください。
対象者
宇治市内在住のひとり親家庭の親(20才未満の子を扶養している方)
支給要件
- 児童扶養手当の受給者、または同等の所得水準であること
- 養成機関のカリキュラムが6月以上あり、対象資格の取得が見込まれること
- 仕事または育児と修業との両立が困難であること
- 過去に本事業による給付を受けていないこと
- 求職者支援制度における職業訓練受講給付金など、同種の給付を受けていないこと
※父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始した方
対象資格
看護師(准看護師を含む)、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、理容師、美容師、調理師、歯科衛生士、歯科技工士、社会福祉士、製菓衛生師、シスコシステムズ認定資格等
6月以上のカリキュラムが対象
支給期間
修業期間の全期間(上限48か月)
支給額
| 課税・非課税 | 給付額 | 課程修了までの期間の最後の12か月 |
|---|---|---|
| 市町村民税非課税世帯 | 月額100,000円 | 月額140,000円 |
| 市町村民税課税世帯 | 月額 70,500円 | 月額110,500円 |
※申請月分から支給します。
| 課税・非課税 | 支給額 |
|---|---|
| 市町村民税非課税世帯 | 50,000円 |
| 市町村民税課税世帯 | 25,000円 |
※卒業後に支給します。
申請手続
必ず事前にご相談ください。
訓練促進給付金は、修業を開始した日以降に申請できます。
申請日の属する月から支給されます。申請が遅れると、その期間は支給されませんのでご注意ください。
マイナンバーについて
平成28年1月からマイナンバーの利用開始に伴い、高等職業訓練促進給付金の手続きの際には、マイナンバーの記入が必要です。マイナンバーの確認できる書類と本人確認書類をお持ちのうえ、お手続きください。
詳しくはこども福祉課窓口におけるマイナンバー確認と本人確認について(別ウインドウで開く)。
高等職業訓練促進資金の貸付
高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指し、将来京都府内等で取得した資格を活かして就職しようとする京都府内在住のひとり親家庭の親に、入学準備金・就職準備金を貸し付けます。
詳しくは、京都府社会福祉協議会のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
高等職業訓練促進給付金を受給している方が対象です。高等職業訓練促進給付金と併せて事前にご相談ください。
貸付限度額
入学準備金(養成機関への入学時の貸付金) 50万円
就職準備金(養成機関の課程を修了し、資格取得時の貸付金) 20万円
利子
- 保証人を立てる場合 : 無利子
- 保証人を立てない場合 : 返還の債務の履行猶予期間中は無利子、履行猶予期間経過後は年1.0%
保証人
原則、保証人1名が必要。ただし保証人を立てないこともできます。(この場合、履行猶予期間経過後は利子が付与されます。)
貸付を受けようとする者が未成年の場合は、法定代理人が保証人となります。
返還免除
下記のすべての要件を満たした場合、返還は免除されます。ただし、要件を満たさない場合は、貸付金を返還していただくことになります。
- 養成機関を修了し、かつ資格を取得した日から1年以内に就職
- 京都府内等において、取得した資格が必要な業務に5年間引き続き従事
高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
高卒認定試験の合格を目指し、民間事業者などが実施する対策講座を受講する場合に費用の一部を支給します。
必ず事前にご相談ください。
対象者
宇治市内在住のひとり親家庭の親(20才未満の子を扶養している方)と20歳未満の児童
支給要件
- 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること
- 高等学校を卒業していないこと(中退を含む)
- 高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であること
- 過去に本事業による給付を受けていないこと
支給額
【受講開始時給付金】
受講開始時に、申請者が支払った受講費用(※)の4割相当額(4,000円以上、上限:通信制 10万円 通学/通信通学併用 20万円)を支給
【受講修了時給付金】
受講修了時に、受講費用(※)の5割相当額から受講開始時給付金として支給された額を差し引いた金額(4,000円以上、受講開始時給付金と合わせて上限:通信制 12万5千円 通学/通信通学併用 25万円)を支給
【合格時給付金】
受講修了日から2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に、申請者が支払った受講費用(※)の1割相当額(受講開始時給付金、受講修了時給付金とあわせて上限:通信制 15万円 通学/通信通学併用30万円)を支給
※次の費用は受講費用に含まれませんので、ご注意ください。
- 高等学校卒業程度認定試験の受験料
- 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費
- 講座の補講費
- 受講施設が実施する各種行事参加に係る費用
- 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用
- 受講のための交通費
申請手続
必ず受講前に申請してください。
(受講前)講座の指定申請→指定決定→高卒認定試験合格のための講座を受講
★給付金を受け取るには、それぞれ以下の期日までに申請してください。
受講開始時給付金: 受講開始後30日以内に支給申請
受講修了時給付金: 講座修了後30日以内に支給申請
合格時給付金: 高卒認定試験に全科目合格後40日以内に支給申請
★母子・父子自立支援員が、就労や生活に関する相談を行っています
次の曜日に相談ができます。(ただし祝日除く)
月、水、金曜日の午前8時30分~午後4時00分(なるべくご予約ください)
予約先:0774-20-8733(こども福祉課)
積極的にご活用ください!