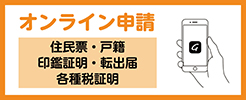本文
マイナンバーカード(個人番号カード)について
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴い、平成28年1月以降、希望者に対してマイナンバーカード(個人番号カード)が交付されています。
このページには、
⑴マイナンバーカードの説明
⑵マイナンバーカードの申請方法
⑶マイナンバーカードの受け取り方
⑷マイナンバーカードに関する問い合わせ先
を記載しています。
トピックス
マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書をご利用いただけます。
マイナ保険証は、患者本人の健康・医療情報に基づくより良い医療の提供、緊急時の活用などのメリットがあり、医療DXを進める上での基盤です。12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなります。
マイナ保険証を基本とする仕組みに移行するに当たっては、全てのかたが安心して確実に保険診療を受けることができるよう、最大1年間※は、現行の健康保険証を使用可能とし、デジタルとアナログの併用期間を設けることとしています。
さらに、マイナ保険証を保有しないかたには、現行の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」を無償で申請によらず交付することとしており、医療機関の窓口で「資格確認書」を提示することにより今までと変わらず保険診療を受けることができます。
また、75歳以上のかたや65歳以上75歳未満のかたで一定の障害があると後期高齢者医療広域連合から認定を受けたかた(後期高齢者医療制度の被保険者)については、令和7年7月末までの間における暫定的な運用として、現行の健康保険証が失効するかたに対して資格確認書を無償で申請によらず交付します。
そのため、後期高齢者医療制度の被保険者におかれては、当分の間、申請は不要です。
※:12月2日時点で有効な健康保険証は最大1年間。有効期限が2025年(令和7年)12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はその有効期限まで。
政府広報オンライン
マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。<外部リンク> 
顔認証マイナンバーカードについて
顔認証マイナンバーカードとは
暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔確認または目視に限定した、暗証番号設定が不要なマインバーカードです。
顔認証マイナンバーカードで利用できるサービス
- 健康保険証としての利用
- 券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類としての利用
顔認証マイナンバーカードで利用できないサービス
- マイナポータル
- 各種証明書のコンビニ交付
- その他オンライン手続き等、暗証番号の入力が必要な手続き
健康保険証利用の申込について
顔認証マイナンバーカードでは、マイナポータルやセブン銀行ATMにて健康保険証利用の申込をすることができません。医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーで申し込みが可能です。
※通常のマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに切り替える場合は、事前に健康保険証利用の申込をしてください。
取得方法
これからマイナンバーカードを受け取る方
本人が来庁して受け取る場合
顔認証マイナンバーカードの取得を希望する旨を窓口でお伝えください。
必要書類等
通常のマイナンバーカードの受け取りと同様です。当ページのマイナンバーカードの受け取り方についてをご覧ください。
代理人が来庁して受け取る場合
申請者本人が交付通知書の暗証番号設定欄で「(2)いずれかの暗証番号も設定しない」にチェックを入れ、代理人が必要書類とともに持参してください。
※お手持ちの交付通知書にチェック欄がない場合は、交付通知書の空いている場所に「いずれの暗証番号も設定しない」旨を本人が記入してください。
必要書類等
通常のマイナンバーカードの受け取りと同様です。当ページのマイナンバーカードの受け取り方についてをご覧ください。
既にカードをお持ちの方
顔認証マイナンバーカードへの切り替えには利用者証明用電子証明書が必要になるため、利用者用明用電子証明書の発行を併せて行う必要があり、かつ代理人が来庁する場合は申請当日に処理が完了しない場合があります。
本人が来庁する場合
- マイナンバーカード
代理人が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(有効期限内のマイナンバーカード、運転免許書、パスポート等官公署発行の顔写真付きのもの)
- 委任状
令和6年3月1日よりマイナンバーカードを使って住民票の写しと印鑑登録証明書をコンビニエンスストアで取得することができます。また、スマートフォンとマイナンバーカードを使って、オンラインで住民票や印鑑登録証明、税関係証明などの交付請求や、転出届を行うことができます。
オンライン申請のページには下のバナーからお進みください。
オンライン申請についてのお問い合わせは<0774-39-9287>まで
マイナンバーカード(個人番号カード)とは?
- マイナンバーカードはプラスチック製の顔写真付きICカードです。
- 表面には氏名・住所・生年月日・性別・顔写真・有効期間が、裏面にはマイナンバー(個人番号)・氏名・生年月日が記載されています。
- マイナンバー(個人番号)の提示と本人確認がマイナンバーカード1枚でできます。
- 初回の交付手数料は無料です。紛失・汚損・旧カードの返納のない場合の更新等にかかる再交付手数料は1,000円(電子証明書が不要な場合は800円)です。
- マイナンバーカードには有効期間があります。 18歳以上の場合は発行から10回目の誕生日、18歳未満の場合は発行から5回目の誕生日までです。
(令和4年4月1日以降は成年年齢が18歳となることから、18歳以上の方については同日以降に申請されると発行から10回目の誕生日が有効期限となります。)
※住民基本台帳カードとマイナンバーカードの重複所持はできません。住民基本台帳カードをお持ちの方は、マイナンバーカード交付時に回収させていただきます。
マイナンバーカードでできることは?
- 本人確認書類として使えます。個人番号カードは写真つきの公的な本人確認書類として利用していただくことができます。
- マイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用していただくことができます。
- 電子証明書を標準搭載していますので、公的個人認証サービスの利用が可能です。これにより国税電子申告(e-Tax)等の電子申請のサービスを受けることができます。
- マイナポータルが使えるようになります。
- 令和3年10月からは健康保険証としての利用が可能となっています。
- 令和4年1月には住民票や印鑑登録証明などの請求や転出届を、令和4年3月には税関係証明の請求をスマートフォンとマイナンバーカードで行うことができるようになりました。
- 令和6年3月1日よりマイナンバーカードを使って住民票の写しと印鑑登録証明書をコンビニエンスストアで取得することができます。
通知カードや個人番号通知書とは何が違うの?
<通知カード>
紙製のカードで、「住所」・「氏名」・「性別」・「生年月日」・「マイナンバー(個人番号)」が記載されています。
令和2年5月25日以降は新規発行・再発行・記載事項の変更は行っておりません。
通知カードの記載事項と住民票の記載事項が一致する場合に限り、「マイナンバー(個人番号)を証明する書類」として使っていただけます。(「身分証明書」として利用することはできません。)
<個人番号通知書>
令和2年5月25日以降に通知カードに代わって発行が開始されており、「氏名」・「生年月日」・「マイナンバー(個人番号)」が記載されています。
個人番号通知書は「マイナンバー(個人番号)を証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。
マイナンバーカードの申請方法について
マイナンバーカードが必要な方は、まず交付申請を行ってください。
マイナンバーカードの交付申請にはいくつかの方法があります。パソコンやスマートフォンによるオンライン申請の場合には、申請書IDやQRコードが記載された申請書が必要です。この申請書は通知カードまたは個人番号通知書とセットで送付されているほか、令和4年3月以降に改めて申請書が送付されています。それらの申請書がお手元にない場合は宇治市役所マイナンバーカード専用窓口までご連絡ください。
なお、申請方法は当ページに記載のとおりですが、申請のお手伝いを希望される方を対象に市内の公共施設や商業施設でサポートを行う「出張申請サポート」を実施していますので、申請のお手伝いを希望される方は出張申請サポートをご利用ください。(詳細は出張申請サポートの特設HP<外部リンク>でご確認ください)
郵送による申請
「通知カード」または「個人番号通知書」と一緒に「個人番号カード交付申請書」が同封されています。個人番号カード交付申請書に必要な情報を記載していただき、ご本人の顔写真を貼り、同封してある返信用封筒に入れて郵便ポストへ投函してください。返信用封筒の差出有効期間が切れているものでも、令和7年5月31日まで有効です。お持ちの封筒に切手を貼って、下記の送付先へ送付してください。
送付先:〒219-8732 日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構 個人番号カード交付申請書受付センター 行
また、個人番号カード総合サイト<外部リンク>では白紙の申請書や申請書送付用封筒の宛名(切手不要)をダウンロードすることもできます。白紙の申請書を使用される場合、個人番号の記入漏れや記入誤りがありますと申請不受理となる場合やカードが出来上がるまで相当な時間を要する場合がありますので、ご注意ください。
スマートフォンによる申請
スマートフォンで顔写真を撮影し、交付申請書のQRコードから申請用webサイトにアクセスし、画面案内にしたがって申請してください。
申請方法はこちら(個人番号カード総合サイト スマートフォンによる申請方法)<外部リンク>
パソコンによる申請
デジタルカメラで顔写真を撮影し、申請用Webサイトにアクセスし、画面案内にしたがって申請してください。
申請用Webサイトはこちら<外部リンク>
申請方法はこちら(個人番号カード総合サイト パソコンによる申請方法)<外部リンク>
まちなかの写真機による申請
マイナンバーカードの申請に対応した証明写真機から申請することができます。
申請方法はこちら(個人番号カード総合サイト まちなか写真機からの申請方法)<外部リンク>
マイナンバーカードを紛失・破損したなどの理由による再交付申請
以下のような場合には、マイナンバーカードの再交付申請を行うことができます。
再交付が必要な場合の例
<有料での再交付(1,000円/電子証明書が不要な場合は800円)>
- マイナンバーカードを紛失・焼失・廃棄した場合
- マイナンバーカードを汚損・棄損・破損し、使用不可能な状態となった場合
- 市外からの転入後、所定期間内にマイナンバーカードの券面記載事項変更手続き(継続利用手続き)を行わず、マイナンバーカードが失効した後に、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
- 在留期間に限りのある外国籍市民の方で、在留期間延長後にマイナンバーカードの有効期間変更手続きを行わず、当初の有効期限を過ぎてしまった場合
- マイナンバーカードを一旦返納した後、再度新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
<無料での再交付>
- 表面サインパネルの記載事項が満欄になり、新たな住所や氏名等の追記ができなくなった場合
- 海外から転入し、マイナンバーカードの再交付を希望する場合
(海外転出時にマイナンバーカードをお持ちの場合でも、海外転出に伴い失効しています。必要に応じてマイナンバーカードの再交付申請を行ってください。)
(新しいカードのお渡し時に前のマイナンバーカードをお持ちください。前のマイナンバーカードがない場合は有料でのお渡しとなります。) - マイナンバーカードの有効期限が切れるため、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
(在留期間に限りのある外国籍市民の方の在留期間が延長される場合は、マイナンバーカードの有効期限が切れる前に有効期間変更手続きを行ってください。有効期限内に手続きされないと、マイナンバーカードは失効します。また新しいマイナンバーカードは有料での交付となります。)
無料での再交付に該当する場合でも、新しいマイナンバーカードのお渡し時に前のマイナンバーカードを返却いただけない場合は有料での再交付となりますので、ご注意ください。
なお、マイナンバーカードの有効期限が切れる場合には、3か月前を目安として再交付申請のご案内が届きます。(在留期間に限りのある外国籍市民の方を除く)
その他の事情により再交付申請を希望される場合は、宇治市役所マイナンバーカード専用窓口までお問い合わせください。
マイナンバーカードの受け取り方について
マイナンバーカードは地方公共団体システム機構によって作成された後、宇治市に送付されます。
送付されたカードの検品や事前設定を行った後に、「交付通知書(ハガキ)」を転送不要で住民登録地のご住所へお送りしますので、交付通知書が届きましたら宇治市役所マイナンバーカード専用窓口まで受け取りにお越しください。
なお、申請から交付通知書の送付まで概ね1月から1月半程度かかります。
受け取り場所
市役所1階ギャラリーコーナーのマイナンバーカード専用窓口です。
受付時間は平日の午前8時30分から午後4時30分です。
受け取りに来ていただく方
マイナンバーカードを間違いなくご本人にお渡しするために、カードのお渡し時にカードの写真によりご本人確認を行いますので、ご本人が受け取りにお越しください。
加えて、15歳未満の方や成年被後見人の方は法定代理人も一緒にお越しください。
但し、ご本人が病気、身体の障害等のやむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人による受け取りが可能です。
やむを得ない理由は次のとおりです。
- 成年被後見人
- 被保佐人及び被補助人
- 中学生、小学生及び未就学児
- 75歳以上の高齢者
- 病気により病院等に入院している場合
- 障害により各種手帳が交付されている場合
- 施設入所している場合
- 要介護・要支援認定の認定を受けている場合
- 妊婦
- 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など、長期間に渡って宇治市外で就労状態にあるため来庁が困難と認められる場合
- 海外留学している場合
- ご本人が高校生・高専生の場合
- ひきこもり状態にある方
※仕事が忙しい、通勤の都合などはやむを得ない理由には該当しません。
必要書類(ご本人が来庁される場合)
(1) 交付通知書(はがき)
(2) 通知カード または 個人番号通知書(紛失されている場合は窓口でその旨お伝えください)
(3) 本人確認書類 (詳しくは下表「本人確認書類一覧」をご覧ください)
下表「本人確認書類一覧」のA欄から1点 または B欄から2点
(交付通知書なし・通知カードまたは個人番号通知書ありの場合は A欄2点 または A欄1点+B欄1点 または B欄2点)
(交付通知書・通知カード・個人番号通知書のいずれも持参されない場合は A欄2点 または A欄1点+B欄1点)
(4) 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
15歳未満の方や成年被後見人の方の場合は、さらに次の2点
(5) 同行する法定代理人の本人確認書類
下表「本人確認書類一覧」のA欄から1点 または B欄から2点
(6) 代理権の確認書類(戸籍謄本その他の資格を証明する書類):本人が15歳未満で法定代理人と同一世帯で親子関係にある場合、本籍地が宇治市の場合は不要
|
A欄 住民票記載事項と一致するもの |
住民基本台帳カード(写真付き)、マイナンバーカード、運転免許証 |
|
|
B欄 「氏名」+「住所」 |
海技免状・電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証 |
|
|
交付対象者が病院や施設に入所していて、上記の書類が不足する場合 |
次の様式に本人顔写真を貼付して、病院長や施設長の証明を受けてください。B欄の本人確認書類とすることができます。 また、本人顔写真はマイナンバーカードの券面写真との確認に使用するため、加工等がされていない本人確認が確実に行えるものをご用意ください。 個人番号カード顔写真証明書(施設用)の様式はこちら [PDFファイル/201KB] |
|
| 交付対象者が在宅で保険医療・福祉サービスを受けていて、上記の書類が不足する場合 | 次の様式に本人顔写真を貼付して、介護支援専門員(ケアマネージャー)とその所属する事業者の長の証明を受けてください。B欄の本人確認書類とすることができます。 また、本人顔写真はマイナンバーカードの券面写真との確認に使用するため、加工等がされていない本人確認が確実に行えるものをご用意ください。 個人番号カード顔写真証明書(在宅介護用)の様式はこちら [PDFファイル/208KB] |
|
| 交付対象者が18歳未満及び成年被後見人で、上記の書類が不足する場合 | 次の様式に本人顔写真を貼付して法定代理人が内容を証明したものを、B欄の本人確認書類とすることができます。 また、本人顔写真はマイナンバーカードの券面写真との確認に使用するため、加工等がされていない本人確認が確実に行えるものをご用意ください。 個人番号カード顔写真証明書(18歳未満及び成年被後見人用)の様式はこちら [PDFファイル/5KB] |
|
| 交付対象者がひきこもり状態にある方で、上記の書類が不足する場合 | 次の様式に本人顔写真を貼付して、公的な支援機関の職員とその支援機関の長の証明を受けてください。B欄の本人確認書類とすることができます。 また、本人顔写真はマイナンバーカードの券面写真との確認に使用するため、加工等がされていない本人確認が確実に行えるものをご用意ください。 個人番号カード顔写真証明書(ひきこもり状態にある方用)の様式はこちら [PDFファイル/8KB] |
|
代理人による受け取りについて
下記のやむを得ない理由により、代理人による受け取りを希望される場合、より厳密に本人確認を行う必要がありますので、必要となる本人確認書類(ご本人分と代理人分)の要件が厳しくなります。
| 対象者(やむを得ない理由) | それを証する書類 |
|---|---|
| 成年被後見人 | 代理権を証する書類 |
| 被保佐人、被補助人 | 代理権を証する書類 |
| 中学生・小学生・未就学児 | 申請者の本人確認書類 |
| 75歳以上の高齢者 | 申請者の本人確認書類(委任状に外出困難である旨の記載が必要) |
| 長期入院者 | 診断書、入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書※ |
| 障害のある方 | 障害者手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証等、療育手帳 |
| 施設入所者 | 入所証明書類、施設長が作成する顔写真証明書※ |
| 要介護・要支援認定者 | 介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネジャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書※ |
| 妊婦 | 母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書、受診券 |
| 長期出張(国内外)者、長期に航行する船員など | 査証の写し (国内の場合、会社からの長期出張がわかる書類) |
| 海外留学している方 | 留学先の学生証の写し |
| 高校生・高専生 | 学生証、在学証明書 |
| ひきこもり状態にある方 | 公的な支援・相談機関が作成する顔写真証明書 |
必要書類(代理人が来庁される場合)
(1)申請者の交付通知書(はがき)
(2)申請者の通知カード または 申請者の個人番号通知書(紛失されている場合は窓口でその旨お伝えください)
(3)申請者の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
(4)申請者の本人確認書類
上表「本人確認 一覧」のA欄2点、またはA欄1点+B欄1点、またはB欄3点(うち1点は本人の顔写真付きのもの)
(5)来庁できないやむを得ない理由を証する書類など(上表「対象者とそれを証する書類」をご覧ください)
(6)代理人の本人確認書類 (詳しくは上表「本人確認書類一覧」をご覧ください)
上表「本人確認書類一覧」のA欄から2点、またはA欄から1点+B欄1点
※ お問い合わせの多い要件を記載しています。詳しくは、リンクページをご確認ください。
- 病気により病院等に入院している場合・障害により各種手帳が交付されている場合・要介護・要支援認定を受けておられる場合はこちらのページへ
- 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など、長期間に渡って宇治市外で就労状態にあるため来庁が困難と認められる場合はこちらのページへ
- ご本人が中学生・小学生・未就学児の場合はこちらのページへ
受け取り時の手続き
マイナンバーカードをお渡しする際に、4種類の暗証番号を設定していただきます。
| 種類 | 設定 | 用途 |
|---|---|---|
| 1 署名用電子証明書用 |
英数字6文字以上16文字以下の暗証番号
|
e-Taxなどインターネットで電子申告を行う際などに使用 |
| 2 利用者証明用電子証明書用 | 数字4文字(※) | マイナポータルを利用する際などに使用 健康保険証利用申込、公金受取口座の登録でも使用 |
| 3 住民基本台帳用 | 数字4文字(※) | 転入手続きやカードの住所・氏名等の変更手続きの際などに使用 |
| 4 券面事項入力補助用 | 数字4文字(※) | 個人番号や基本4情報(住所、氏名、生年月日、性別)を確認し、テキストデータとして利用する際に使用 ワクチン接種証明アプリでも使用 |
※2から4の数字4文字の暗証番号は同じ番号でも設定できます。
<注意>1は5回連続、2・3・4は3回連続で入力を誤ると使用できないようになり、再設定が必要となります。なお1については、2が分かる場合に限り、マイナンバーカードの読み込みができるスマートフォンとコンビニ等のキオスク端末を利用した再設定が可能ですが、2・3・4の再設定は市役所以外ではできません。
マイナンバーに関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
平日9時30分~20時00分 土曜日・日曜日、祝日9時30分~17時30分(※)
※1番については、平日・土曜日・日曜日、祝日ともに9時30分~20時00分
マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難による一時利用停止については、24時間365日対応しています。
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
1番 マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード・コンビニ等での証明書交付サービスに関するお問い合わせ
2番 マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難について
3番 マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
4番 マイナポータル及びスマホ用電子証明書に関するお問い合わせ
5番 マイナンバーカードの健康保険証利用に関する問い合わせ
6番 公金受取口座登録制度に関するお問い合わせ
マイナンバーカードに関するお問い合わせ
個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)
0570-783-578
※ナビダイヤルは通信料がかかります。
8時30分~20時00分 (年末年始 12月29日〜1月3日を除く)
マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
一部IP電話等で上記どちらのダイヤルに繋がらない場合(有料)
050-3818-1250
外国語対応
個人番号通知、通知カード、マイナンバーカード、マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止
0120-0178-27
0570-064-738
※上記番号がつながらない場合(有料)
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語
24時間※
タイ語・ネパール語・インドネシア語
9時00分~18時00分
ベトナム語・タガログ語
10時00分~19時00分
※20時00分~翌9時29分はマイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止のみの受付となります。
マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
0120-0178-26
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・タイ語・インドネシア語・タガログ語・ネパール語
平日 9時30分~20時00分
土曜日・日曜日、祝日 9時30分~17時30分(年末年始除く)
ホームページ
マイナンバー制度について詳しくお知りになりたい方は、内閣府のマイナンバー制度のホームページもご覧ください。(下のバナーをクリックしてください。)
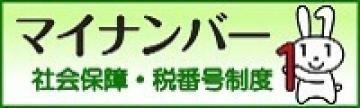
マイナンバー(社会保障・税番号制度)(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
マイナンバーカードについて詳しくお知りになりたい方は、地方公共団体情報システム機構のマイナンバーカード総合サイトもご覧ください。(下のバナーをクリックしてください。)
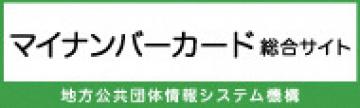
マイナンバーカード総合サイト(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
マイナポータルには、下のバナーからアクセスすることができます。
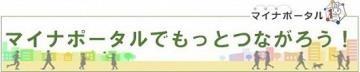
サービストップ | マイナポータル(別ウィンドウで開く) <外部リンク>