本文
宇治市議会(行政視察報告 令和6年度) 1
産業・人権環境常任委員会の行政視察報告
年月日: 令和6年5月7日(火曜日)~5月9日(木曜日)
視察先: つくば市(茨城県)、町田市(東京都)、川越市(埼玉県)
出席委員:中村委員長、角谷副委員長、松峯、山崎、徳永、稲吉、藤田の各委員
執行部: 脇坂産業観光部長、前田人権環境部長
つくば市(5月7日)
【調査項目】
つくばスタートアップパークに係る取組について
『市の概要』
- 市制施行:昭和62年11月30日
- 人口:25万6,483人(令和6年5月1日現在)
- 面積:283.72平方キロメートル
1.つくばスタートアップパークに係る取組について
(1)概要について
つくばスタートアップパークは、起業家・大学・研究機関、投資家、金融機関等のスタートアップに関わる全ての人々のハブ拠点となり、スタートアップの創業と成長をサポートするため、大学や研究機関が集積するつくば市の強みを生かし、テクノロジー系スタートアップ支援を核としたつくば市が運営するインキュベーション施設である。施設内には、一時的な作業(ドロップイン)やオフィス(定期利用)として24時間365日利用できるコワーキングスペース、スタートアップや起業に関するセミナーやイベントを開催できるセミナールーム、誰でも気軽に出入りが可能で多様な人々の交流や対話が生まれる交流スペースなどがある。
スタートアップパークの建物は、平成28年にNICT(国立研究開発法人情報通信研究機構)からつくば市に無償譲渡されたものである。つくば市では平成21年4月にNICTから無償貸与された2階をベンチャー向け貸しオフィスとして運営していたが、平成31年10月から1階をつくばスタートアップパークとしてリニューアルオープンし、各種スタートアップ支援を開始した。なお、再整備では、国土交通省の社会資本整備総合交付金を活用した。
(2)主な取組について
取組としては、会社を立ち上げるための手順やサポートなどを行うための専門員の常駐、専門家(士業)相談、毎週水曜日の夜のイベントの開催など、つくば市のスタートアップ支援の出発点となるように取り組むとともに、誰でも気軽に立ち寄れるスペースや、経理、特許などに関する様々なイベントも開催し、仲間との出会いや交流を生む場を目指している。また、起業、チャレンジ精神の醸成施策として、人材育成に力を入れている。これはつくば市内の研究機関と大学の研究者や職員を対象にして、筑波大学とアントレプレナー育成プログラムの実施に取り組んでいる。
(3)つくば市スタートアップアップ戦略について
平成30年からの第1期つくば市スタートアップ戦略は新規参入の実現に向けて23の施策を策定し、そこから本当に必要な施策を徐々に絞り込むという手法を取った。成長段階が潜在的企業希望期から成長期までの幅広い施策として、行政が税金を使うべきポイントが見えてきたところである。
第2期つくば市スタートアップ戦略では、「起業文化の醸成により、人の成長と科学技術が社会に生かされるまち」というビジョンの下、人的資源と研究成果を生かしたスタートアップ創出とスタートアップが成長できるエコシステムの醸成に絞り込んだ。研究者に事業化するという道もあるという意識の醸成が市にとって重要と考え、限られた予算でやるべきことはやりつつも、それ以外のところは、金融機関や大企業との連携などの機能を使って成長できるよう取り組んでいる。
(4)新規で起業した中小企業者の定着率について
定着率についてのデータはなく、把握している中では3者が市外へ移転している。なお、つくばスタートアップパークでの起業件数については45件となっている。ただ何をもって成功とするのかという基準を設けていないため評価がしづらい。
(5)市内経済への波及効果について
波及効果については算出しておらず、つくばスタートアップパークによる市内の新規中小企業者を支援及び育成することで、新たな雇用が生まれていると考えている。
(6)今後の課題について
小中学校への先生を含むアントレプレナーシップ教育や経営人材の掘り起こしが課題である。
(7)その他
委員からは、つくばスタートアップパークの来場者について、研究者ではない事業者への補助金などの支援制度について、イベントを初めて開催する際の案内の周知方法について、イベントのテーマについて、家賃補助について、コワーキングスペースの利用方法及び利用状況について、地元企業とのつながりについて、貸しオフィスについて、市長の肝煎りの事業なのかについて、スタートアップでの首長同士のつながりについて、海外の事例を参考にしているのかについて、スタートアップ推進室の職員の平均年齢について等の質疑がなされた。
「つくば市視察の様子」
町田市(5月8日)
【調査項目】
町田市バイオエネルギーセンターについて
『市の概要』
- 市制施行:昭和33年2月1日
- 人口:43万927人(令和6年5月1日現在)
- 面積:71.55平方キロメートル
1.町田市バイオエネルギーセンターについて
(1)概要について
町田市バイオエネルギーセンターは令和4年1月に稼働を開始し、熱回収施設・バイオガス化施設・不燃粗大ごみ処理施設が一体となった施設である。現在、管理棟の北側に、資源化物等を場外に搬出するまで保管するストックヤード棟を整備中であり、完成予定の令和6年9月に竣工となる。事業は設計・建設工事・運営を一体で行うDBO方式を採用している。DBO事業での運営期間は20年となっている。
施設の処理能力は、熱回収施設が129トン/日が2炉、バイオガス化施設25トン/日が2基、不燃・粗大ごみ処理施設が47トン/5hとなっている。
(2)事業実施に至る背景について
平成21年6月から「町田市廃棄物等推進協議会」で審議を行い、平成23年4月に町田市一般廃棄物資源化基本計画を策定した。この計画では、ごみとして処理する量を40%削減することを全体の目標として掲げ、その目標達成のため個別目標として生ごみの資源化策でバイオガス化による処理を位置づけた。その後、町田市資源循環型施設整備基本計画検討委員会では、バイオガス化施設を含めた新しいごみ処理施設整備の検討を行い、平成25年4月に町田市資源循環型施設整備基本計画を策定し、焼却施設・バイオガス化施設・不燃粗大ごみ処理施設を同一敷地内に一体で設置し整備することにした。
(3)主な取組及びその成果について
1.発電効率の向上
新しい焼却施設は、蒸気タービン発電機の発電効率が格段に上がり、以前の施設と比較して売電量が増えた。
2.二酸化炭素排出量の削減
町田市では、2050年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロを目指す町田市ゼロカーボンシティ宣言をしている。この宣言では、町田市バイオエネルギーセンターにおける廃棄物バイオマス発電は重要であると位置づけている。バイオガス化施設でバイオガスを作ることにより、生ごみをそのまま生ごみとして燃やすよりも年間で約745トンの二酸化炭素の発生量を削減することができる。
3.見学者コースの充実
町田市内の小学3・4年生が校外学習で見学に来ることから、ごみ処理施設の仕組みだけではなく、ごみの減量やリサイクルについてゲーム感覚で学ぶことができる見学コースとしている。
(4)バイオガスによる発電状況と地域での消費について
バイオガス発電は一般廃棄物の焼却による発電よりも、固定価格買取制度(FIT制度)により買取価格が高く設定されていることから、積極的に売電をしている。売電のほか、電力の地産地消を目指し、令和6年6月から町田市内の下水処理場へ送電を始める。
(5)今後の課題と取組について
令和4年1月の町田市バイオエネルギーセンターの本格稼働後、消防車が出動する事態となったリチウムイオン電池が原因と思われる火災が4件発生している。昨年11月の火災では、発酵できるごみを取り出す選別装置が燃えたことにより、現在バイオガス化施設が稼働していない。現場では手選別の作業員を増員しているが、対応が難しい状況である。取組としては、令和4年7月から有害ごみの日(乾電池の回収日)に小型充電式電池とボタン電池の行政による回収を始めた。また、リチウムイオン電池の選別が機械でできるように、メーカーと共同で試作品を作っている。
(6)その他
委員からは、地域コミュニティーなどとの連携プロジェクトがあるのかについて、FIT制度の適用期間について、バイオガス発電の売電価格について、災害等で停電した場合の自家発電について等の質疑がなされた。
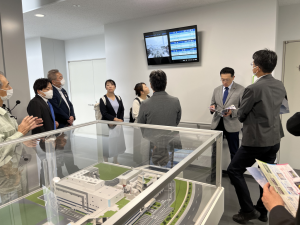
「町田市視察の様子」
川越市(5月9日)
【調査項目】
川越市観光振興計画について
『市の概要』
- 市制施行:大正11年12月1日
- 人口:35万3,201人(令和6年5月1日現在)
- 面積:109.13平方キロメートル
1.川越市観光振興計画について
(1)概要について
第二次川越市観光振興計画は計画期間が平成28年度から令和7年度の10年間となっており、策定した5年後に中間見直しを予定していた。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の流行と重なったことから、見直しの時期を後ろにずらし、後期は令和4年度から令和7年度までの4年間とした。第二次川越市観光振興計画は、「世界に発信しよう!EDOが粋づくまち 小江戸川越」を基本理念としており、4つの基本方針に67の政策がひもづいている。
(2)指標と成果について
観光客数、外国人観光客数の割合、平均観光消費額など10の指標について、令和7年の目標値に対して、令和5年の実績値をマルまたはバツで評価している。コロナの影響もあり評価がバツの指標もあるが、最終的には全てをマルにできるように計画を進めている。
(3)改訂版について
川越市の課題をしっかりと解決していくという考えの下、課題として下記の5点が挙がった。
1.観光時間が日中の短時間となっており、伸び悩んでいる
2.ICTの活用が不十分である
3.外国人観光客の受入環境が不足している
4.観光客の増加により交通の安全性不足とゴミ環境問題が生じている
5.地域内外の連携が不足している
これらの課題とともに、新たにSDGs、カーボンニュートラルやデジタル技術の進展などの社会状況等も踏まえながら改訂版を策定した。また、オーバーツーリズムを考慮し、単に観光客数という量を求めるのではなく、着実に課題の解決を図ることのできる質を重視するとともに、まちをコントロールしていくという考え方に方向転換した。
(4)インバウンドへの取組について
コロナ以降の主な取組としては、一般社団法人DMO川越を主体として、令和4年度は東京都内で勤務するホテルのコンシェルジュや映像クリエイターを招き、本物の川越文化を体験できるツアー造成に向けたファムトリップを実施し、令和5年度も関係者を招きインバウンド誘客と消費拡大に向けた前年度に近い内容のファムトリップを実施した。その結果、令和5年の外国人観光客数は過去最高の61万5,000人であった。
(5)オーバーツーリズムへの取組について
川越市ではオーバーツーリズムは観光における最重要課題としており、観光庁のオーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業の中の「地方公共団体が中心となった、地域と連携した先駆モデルの創出」に申し込んだ。この補助事業を利用した対策として、観光客の分散化、車両の流入抑制や観光客に対するマナー啓発をテーマに取り組んでいく予定である。観光客の受入れと住民の生活の質の確保を両立しながら、持続可能な観光地域づくりの実現を目指し、関係者や住民への説明を大切にしており、オーバーツーリズムで観光のブレーキをかけるのではなく、引き続き観光客の受入れは継続していく。
(6)その他
委員からは、混雑予報の仕組みについて、外国人観光客数の統計方法について、蔵造りエリアにある店舗の営業時間について、観光客を分散させる場所と時間の考え方について、シェアリングサイクルの利用について、どこの会社のビックデータを利用しているのかについて、観光客数の統計方法について、散策マップにある三つの駅から観光地までの距離について、駅周辺の用地取得について、まちの公衆トイレについて、花火大会の開催について、花火大会への寄附について等の質疑がなされた。

「川越市視察の様子」






